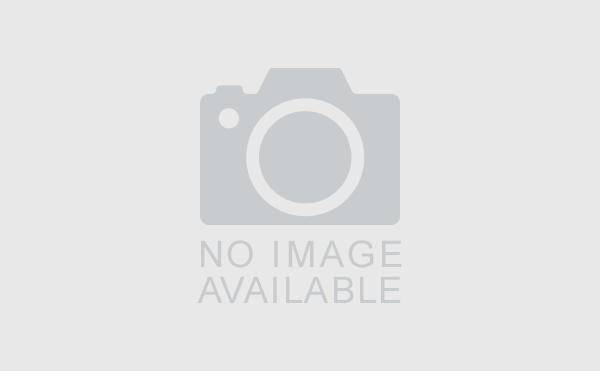小売店の目利き機能、どこへ行った?
今日のガイアの夜明けは、電子書籍に関する話題でした。
その主役は、もちろんipad。
しかし、私の目を引いたのは、危機感を強めた町の本屋さんの映像。
町の本屋さんが抱える問題は、
◎電子書籍・インターネットの普及による書店での売上減少
◎ベストセラー書籍が満足に仕入れられない
という二点。
この二点を解決するために、
◎仕入れる書籍を厳選し、販売する書籍にはPOPを付けて消費者にアピール。
◎ベストセラーよりも既刊本を中心に仕入る。
という方法を取っているという。
ここで、注目したいのは、一つ目の
◎仕入を厳選して、お店でアピール。
という点。
それは、これぞ小売店の原点だと思うから。
そもそも小売店は、世界中にある商品の中から売れそうだと思う商品を仕入れて、店頭で販売するものだと認識しています。
インターネットならまだしも、リアル店舗の場合は場所という制約があるため、仕入商品を厳選しなければなりません。
しかも、売上を上げるには、顧客が買いそうな商品を選ぶ目が必要。
これこそ、小売店の生命線であり、だからこそバイヤー業務は大変重い重責を担うのです。
しかし、ふと近くのスーパーを複数行ってみると、
◎置いてある商品はほとんど同じ。
◎違うのは、価格。
という状況を目にします。
この状況の背後には、
◎商品を厳選するよりも、いかに原価を低くするかということが重要。
というバイヤー業務の変化があるのではないでしょうか。
「少しでも安い商品を消費者は望んでいる。」という考えが強いのかもしれません。
本来小売店が持つべき、目利き機能がそこではあまり機能していない。
町の本屋さんが目利き機能を重要視する要因は、
◎書籍は定価販売であるため。
◎品揃えでは、大型書店やインターネットにはかなわないから。
であるのは、言うまでもありません。
だからと言って、価格を自由に付けられるスーパーが、目利き機能をないがしろにして仕入価格を最優先するのは仕方ない、とは思いません。
やはり、来店してくれる顧客が望む商品を厳選するという機能は、小売店の屋台骨であることには変りない。
そして、自分で厳選した商品をPOPなどを通じてアピールすることは、小売店にとって必須のように思えます。
☆ 本日のま とめ☆
小売店にとって、星の数ほどある商品の中から商品を厳選することは、大変重要な機能である。
この目利き機能は、価格競争が起こりうるスーパーにとっても、屋台骨のような機能である。
☆6/14 の目標 ☆
1 プライベートブログの更新 〇
2 午前7時起床 ×
3 毎朝、鏡の前で笑顔の練習 ×
4 腕立て・腹筋を各30回 ◯
5 部屋・事務所などの掃除をする ×
6 手帳に今日の反省の明 日の希望を書く。×
7 読書(書籍・雑誌)をする 〇
8 毎朝、ツイッターでつぶやく ×
☆ 本日のこぼれ話☆
車でたまに行く酒販店では、店員さんが独自に作ったPOPでその商品特徴が訴えられています。
しかも、そこの商品は、ダイエーやイズミヤなどでは目にしない商品が多い。
珍しい商品があること自体楽しいですが、しかもその特徴がわかりやすく説明されているので、ついつい買ってしまう。
買い物には、安さも必要ですが、それ以上に楽しさも必要。
それ実感できるお店です。
(今 日の言葉)
「本当に優秀な人は、特別扱いされることも拒むものだ。」
(ファー ストリテイリング社長柳井正 「一 勝九敗 (新潮文庫) 」よ り)
※ 当分、私 の好きな書籍「一 勝九敗 (新潮文庫) 」から引用します。