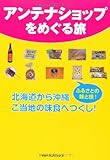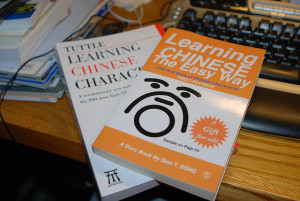エキマルシェ新大阪は食品メーカーの実験場?
無料求人誌のan大阪版を見ていたら、エキマルシェ新大阪が特集されていました。エキマルシェ新大阪とは、3月4日にオープンするJR新大阪駅のショッピングエリア。大阪駅のエキマルシェ同様、飲食店も多く出店するのですが、エキマルシェ新大阪は、大阪とは大きく違います。それは、多くの店舗で食品メーカーが絡んでいるからです。
実際に食品メーカー関連のショップを挙げると、
ぐりこ・やKitchen(グリコのアンテナショップ)
JIM BEAM BAR(サントリーのアンテナショップ)
チキンラーハウス(日清食品のアンテナショップ)
VIA BEER OSAKA(アサヒビール直営のパブ)
があります。まとめると、
食品メーカーアンテナショップ
食品メーカー直営飲食店
に分類できます。(酒類メーカーは食品メーカーに分類)
食品メーカーがアンテナショップ・直営飲食店を運営することで、次のようなメリットを享受できます。
【食品メーカーのアンテナショップ・直営飲食店のメリット】
- 売上増
- ブランドロイヤリティの向上
- 消費者ニーズの把握
1については、ネスレ日本の高岡社長が、年始の日経MJで発言されていることに集約されていると言えるでしょうか。ネスレのネスカフェアンバサダーには、スーパー・コンビニ以外の独自の流通経路を作る目的があるようです。同様に、グリコ・サントリー・日清食品は、エキマルシェ新大阪のアンテナショップで、小売企業に依存しない独自の流通経路を獲得できます。陳列や売価設定など好きな販売方法が取れることは、小売企業経由の販路にはない魅力です。新たな流通を獲得できることで、売上は確実に上昇します。
一方で、新たな流通経路を獲得できるものの、自社で店舗を運営しなければならず、従来にはないコストが掛かるというデメリットがあります。このデメリットを打ち消してくれるのが、直営店舗によるブランドロイヤルティの向上でしょう。少々店舗収益が赤字でも、ブランドロイヤルティが向上することで、他ルートでの販売が伸びれば、十分ペイするからです。例えば、阪神梅田にあるカルビーのグラノやは、店舗収益自体恐らく赤字でしょう。しかし、グラノやによりグラノーラの認知度が上昇することで、シェアナンバーワンのフルグラの販売が伸びれば、赤字を十分賄えるのではないでしょうか。要は、人通りの多い場所でいかにブランドに接する機会を増やすか。エキマルシェ新大阪は、この目的に合致する絶好の場所なのかもしれません。
3は、小売店を介して販売する食品メーカーにとって、消費者との接点はそう多くありません。だから、消費者がどのようなニーズ・ウォンツを持っているかを把握するのは、至難の業。これを可能にしてくれるのが、直営店なのです。直営店での販促とその反応やコミュニケーションを通じて、従来ならばわからなかった消費者ニーズを把握できるかもしれません。それは、今後の商品開発に活かされることになります。
このように、食品メーカーが店舗造成の初期投資と運営コストを掛けてまで直営店舗を出店することは、ある意味実験のようなもの。そのメーカー直営店舗が集積するエキマルシェ新大阪は、まるで実験場のようです。この取組が収益に貢献すれば、メーカーの直営店が今後増えるかもしれません。
☆今日のまとめ☆
食品メーカーがコストを掛けてまで直営店を出すのは、新たな流通経路による売上増、ブランドロイヤルティの向上、商品開発につながる消費者ニーズの把握が期待できるから。
WSJを読むには、基本的な英単語を知っていなければなりません
- 今日のこぼれ話☆
ふるさと納税でいただいた純米酒を飲んでいるのですが、美味しいせいかついつい飲み過ぎてしまいます。
最近は、ワインではなく日本酒ばかりになっています。