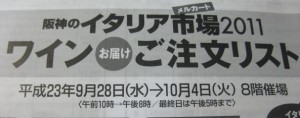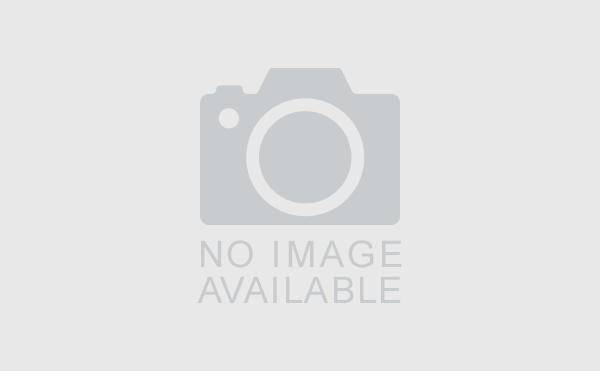阪神のイタリア市場2011、ワインリスト公開からわかることとは?
先週末、2011年9月28日から本日まで行われている、イタリアのフードイベント・阪神のイタリア市場2011に行きました。特に欲しい物があるから行ったというよりも、視察という意味合いが強いですね。
このようなフード関連のイベントは、集客力が強いことで、百貨店ではよく行われます。ただ、そのほとんどは日本の物産展。そう考えると、イタリアにフォーカスしたイベントは珍しいかもしれません。約250銘柄のワインが試飲できるとあって、日本の物産展以上の来客数だったと思います。
このイタリア市場で見つけたのが、上に掲載したワインご注文リスト。これ、どこかで見たことがあります。そう、今年の5月に行われた阪神大ワインフェスタでも同じようなワインリストが配布されていました。もちろん、今回はイタリアンフェアなので、イタリアワインのみの掲載となりますが、販売するワインを公開するという意味では同じ。同じことを行うということは、以前行ったワインリストの公開・配布が成功したということを意味します。
こちらの記事でも書いたのですが、販売するワインの銘柄と価格を記載したワインリストを公開・配布することにはリスクが存在します。その一番大きなリスクとは、競合店に販売商品・価格を知られることです。スーパーや百貨店は、販売商品(特に食料品)やその価格を一般に公開されることをとても嫌います。一部独自商品を取り扱うものの、そのほとんどは競合も販売できる商品であるので、公開されると価格競争に巻き込まれる可能性があるからでしょう。特に、セルフサービスのスーパーではその傾向が強いように思えます。
その販売商品・価格が書かれたワインリストを、来場客なら誰でも取れる形で配布したことには、驚きました。(以前の記事で書いています。)大きな賭けとも言えます。イタリア市場でも同じようなワインリストを配布したことは、この賭けがうまくいったことを表します。恐らく、大ワインフェスタでの売上が、予算を突破したのでしょう。
このワインリストは、そもそも「ワインお届けご注文リスト」とあって、ワイン注文用紙の役割をしています。試飲したワインを買いたいと思った人で、その場で持ち帰らずに自宅まで届けてもらいたい人が、リストに必要本数を記入して、注文カウンターに持ち込みます。試飲する場所と注文カウンターが、別なのです。だから、試飲した場所で買わなくても、注文カウンターで買ってくれるかもしれないので、店員さんは顔色ひとつ変えることなく、また売り込むこともありません。この売り込みプレッシャーがない状態で試飲できるというのが、このワインリストの大きな利点でしょう。阪神百貨店側にとっては、来場客が気軽に試飲ができるので、見込み客の集客効果があります。
さらにワインリストには、ワインの情報(ワイン名・地域・タイプ・味わい・容量・アルコール度数・コメント)が記載されています。さらに、メモ欄もあります。なので、ワイン情報を見ながら試飲ができ、さらにメモまで取れるのです。(会場では鉛筆も配られていたので、メモを書いても特に問題はありません。)試飲結果・評価をメモできることは、ワイン好きにはありがたい環境です。百貨店側にもメリットがあります。それは、当日購入しなかった人が、メモがあることで後日イタリアワインを購入する確率が高まるからです。イタリアワインを買いに行った時に、そのメモを見て注文するかもしれません。イベント後の売上効果を見込めます。
販売するワインを公開することはリスクがありますが、一方で集客効果やイベント後の売上効果もあります。大ワインフェスタに続いてイタリア市場でもワインリストを公開したことは、リスクよりも効果の方が大きかったということではないでしょうか。
☆今日のまとめ☆
阪神のイタリア市場2011では、大ワインフェスタに続いてワインリストを公開・配布。
これは、大ワインフェスタでワインリストを公開・配布したことが成功したことを表します。
販売するワインの銘柄・価格を公開することは、競合他社に知られる可能性があり、価格競争を仕掛けられるリスクがあります。
一方で、気軽に試飲ができることによる集客効果や、メモを取れることによるイベント後の売上効果を見込めます。
リスクよりも効果が大きかったことが、今回のワインリスト公開から読み取れます。
☆ 昨日のこぼれ話☆
昨晩は、今秋初の鍋。
昨年の冬の終わりに買った鍋つゆを使いました。
鴨鍋、おいしいですね。
☆昨日の目標→その結果☆
◎朝6時に起きる→◯
◎毎日情報を発信する→☓
◎毎日仕事以外の人に話掛ける→☓
◎腕立て・腹筋30回→◯
◎自宅のある12階まで歩いて登る、または自転車を30分以上漕ぐ→☓
◎部屋や家の掃除をする→☓