伊勢丹新宿店「100選カタログ」、消費者を購買に駆り立てる媒体の条件とは?
昨日(2012年8月8日)の日経MJに、デパ地下の記事が掲載されていました。
百貨店では国内最大の売り上げを誇る伊勢丹新宿本店(東京・新宿)の地下食品売り場に食べ物以外の隠れた「ヒット商品」がある。エスカレーター近くの棚や売り場の案内所に置かれた宣伝媒体「100選カタログ」だ。掲載された商品の売れ行きは通常の1・5~2倍に跳ね上がり、既存商品の活性化に効果を上げている。(2012年8月8日日経MJより)
伊勢丹新宿店が、食品カタログによってデパ地下の売上げを伸ばしているようです。そのカタログが、「100選カタログ。」
デパ地下の宣伝媒体は、特に珍しいものではありません。たまに、新聞折込チラシが入っていることがあるし、たいていデパ地下に行けば、何かしらチラシが置かれています。先日神戸そごうに行った時にも、白黒のチラシが二種類、ラックに置かれてありました。(チラシにはとても興味があるので、目に入ると持ち帰るようにしています。)
たいていのデパ地下にある宣伝媒体。ただ、それらが売上げに大きく貢献しているかは不明であり、恐らくそれほど大きな効果は発揮していないかと思います。しかし、伊勢丹新宿店の「100選カタログ」は、他のデパ地下媒体とは異なり、売上げに大きく貢献しているようです。
その理由は、記事の中でも述べられています。
売れているものに絞って紹介していることが支持の背景にあるようだ。
(中略)
掲載ルールは「根拠が明確なこと」(武田マネージャー)。(同日日経MJより)
実際のカタログを見て気づかれた方もおられるかと思いますが、単に「売れ筋商品です」「人気商品です」「売上げ第一位です」という表現だけにとどまらず、
どれだけ売れたか
いつ売れたか
を数字で明確に表示しています。例えば、最新号の「夏においしい100選」では、1ページ目に大きな画像とともに本格冷麺が取り上げられていますが、そこには、
販売数:約2000個/6月~9月
と明記されています。この数字が、消費者の信頼を勝ち取り、実際の購買につながっているとのことです。
思えば、チラシやカタログなどの宣伝媒体、さらに店頭では、次のようなフレーズがよく目に入ります。
私たち従業員がおすすめします! (食品スーパーのチラシ)
よく売れています!(小売店店頭のPOP)
おすすめGIFT(お中元のチラシ)
本日のおすすめ(居酒屋のメニュー)
ただし、「おすすめ」「よく売れている」という根拠が示されているものは、ほとんどありません。このような根拠のないフレーズが量産された結果、消費者はその言葉の効果を信じなくなったのではないでしょうか。だからこそ、その根拠を数字で示した伊勢丹新宿店の「100選カタログ」が人気を博しているのだと思います。
BtoBの場合、明確な根拠を示して説明することは当たり前のことです。商談において、単に「売れています」「おすすめです」という文句だけで、売れることはほとんどありません。その根拠となる数字を示さなくては、納得してもらえないからです。そう考えると、BtoCにおいても、BtoBと同じような納得できるコミュニケーションが必要とされるようになったと、捉えることができます。
「100選カタログ」に関して、さらに考えることがあるので、それは次回に述べたいと思います。
☆今日のまとめ☆
伊勢丹新宿店の「100選カタログ」がデパ地下の売上げに貢献しているのは、売れている根拠を数字で示しているから。
「売れています」「おすすめです」などの言葉が量産された結果、消費者はそのような言葉だけに反応しなくなってきている。
BtoB同様、BtoCのコミュニケーションでも納得できる根拠を示す必要がある。
☆What to EAT Yesterday☆
食べたわけではないのですが、伊勢丹の100選カタログを見て、思い出したのがこちらのケーキ。
関西のデパ地下では常連、アンリシャルパンティエのケーキです。
大きいので、まだ買ったことはありませんが、見ているだけで幸せな気分になります。
2人では大きすぎるので、食べるのに3~4人は必要でしょうか。
アメリカのビジネス最新事情メルマガ
今飲んでいるワインのこと知っていますか?
WSJメルマガからスピンアウトした英単語サイトです。
Twitterやっています
FaceBookはほぼ引退しました
Tumblrで年率5%運用するための情報を発信しています。
☆今日のこぼれ話☆
最近、毎日お茶を沸かしています。
それぐらい、お茶を飲んでいるんですね。
夏の麦茶は最高。
伊藤園さん、ありがとう。
☆昨日の目標→その結果☆
◎ 朝6時に起きる→◯
◎ 毎日情報を発信する→◯
◎毎日仕事以外の人に話掛ける→☓
◎腕立て・腹筋30回→◯
◎自宅のある12階まで歩いて登る、または自転車を30分以上漕ぐ→☓
◎部屋や家の掃除をする→☓
◎営業日誌を付ける→☓
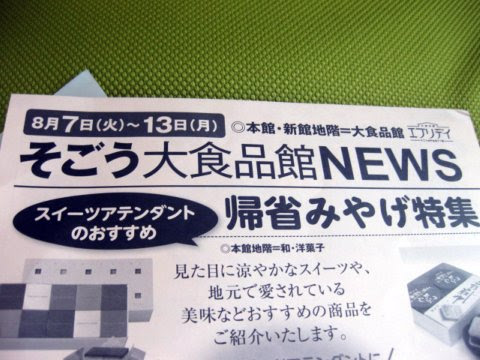

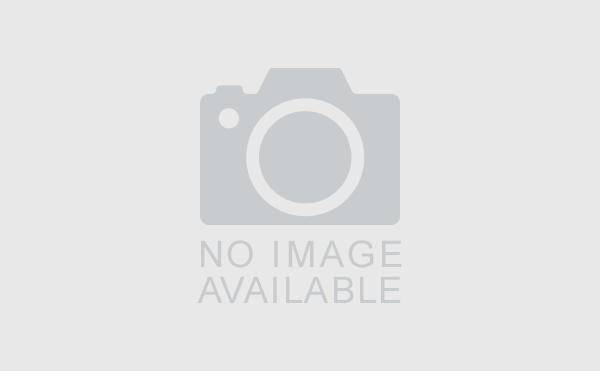
“伊勢丹新宿店「100選カタログ」、消費者を購買に駆り立てる媒体の条件とは?” に対して1件のコメントがあります。