阪神大ワインフェスタがクリアした試飲販売会の課題とは?
先週、梅田の阪神百貨店で行われた阪神大ワインフェスタに行きました。8階の催場で行われた大規模なもので、地下の食料品売場で普段行われている試飲販売とは比較にならないほどの規模でした。
何度か大規模なワイン試飲販売に参加(消費者として)したことがあるのですが、その際に気づいた課題が3つあります。それは、
- 多数のワインを試飲すると、どれが気に入ったのかを忘れてしまう。
- 試飲する際に、店員さんに銘柄を指定する時、慣れないカタカナの商品名が伝わりにくい。
- 買い回りをする時、カゴに入れたワインが重く感じる。
です。
今回の阪神大ワインフェスタでは、これらの課題がクリアされていました。その大きな要因は、試飲販売商品リスト。このリストには、「商品名」「原産国・原産地」「特別価格」「タイプ(白・赤・ロゼ・スパークリング)」「主要品種」「味わい(甘辛・ボディ)」「アルコール度数」「容量」「コメント」が記されてあります。ワインフェスタ入り口で、このリストと鉛筆が配布されています。これらを使うことで、
- リストにメモをすれば、気に入ったワインを忘れずに済む。
- 試飲商品には番号が記されているので、番号を伝えることで試飲したいワインを指名できる。
- リストに注文数を書きこむ欄があり、この欄に数字を書き込み専用カウンターに行けば、ワインの発送手配ができる。
というように、試飲から購入に至るプロセスがかなりスムーズになります。
このリストを配布するにあたっては、阪神百貨店社内でかなり議論になったように思えます。なんせ、どんな商品をいくらで販売しているかという情報は、競合他社(阪急・大丸・三越伊勢丹・その他ワイン販売店)にとって喉から手が出るほど欲しいものなので。そんなリスクを負ってまで配布するということは、それだけこのリストが消費者にとって役立つと認識していたのでしょう。阪神百貨店さんには、頭が下がります。実際、ワインフェスタ会場では、リスト片手に楽しく試飲している方を、多く目にしました。
もしかしたら、阪神百貨店には、さらなる効果を期待していたのかもしれません。その効果とは、
◎イベント終了後も、リストがワインの購入につながる。
というもの。この理屈を説明すると、
- 試飲会場で、気に入ったワインをリストにメモする。
- イベント終了後、ワインを飲みたい気分になる。
- リストの存在に気づき、メモしたワインの中から選ぶ。
- そのワインを阪神百貨店に買いに行く。
になります。つまり、このリストによって、イベントがイベント終了後の購入につながることになります。もしかしたら、阪神百貨店に買いに行かず、ネットで購入するかもしれません。その場合でも、ワインフェスタに出展したインポーターにとっては、売上になります。このように説明することで、阪神百貨店は、インポーターのワインフェスタへの協力を引き出すことができます。
このように、配布された試飲販売商品リストは、イベント内で試飲から購入につなげる手助けをするだけでなく、イベント終了後の購入をも生み出します。単なるリストですが、このリストには大きなマーケティングの仕組みが組み込まれています。
☆今日のまとめ☆
阪神大ワインフェスタでは、配布される試飲販売商品リストによって、試飲から購入に至るプロセスがスムーズになっている。
さらに、リストに気に入ったワインをメモすることで、イベント終了後の購入につながる。
イベント内の売上のみならず、終了後の売上をも生み出すこの商品リストには、大きなマーケティングの仕組みが組み込まれている。
阪神大ワインフェスタは、5/17まで行われています。(動画あり)
☆今日のこぼれ話☆
阪神大ワインフェスタは無料ながら、有料のシェラトンワインフェスティバルと同じかそれ以上に楽しめました。
試飲できるワインは約615種類。
さらに、有名シャトーの有料試飲もあります。
ワイン好きにはたまらないイベントですね。
私が特に印象に残ったのは、RMシャンパン。
小規模生産者が造るシャンパンで、その厳しいルールから生産量はかなり少なく、ほとんどがフランス国内で消費されるそうです。
その貴重なRMシャンパンの魅力を伝えてくれたアールアンドダブリューの田中さん、どうもありがとうございました。
☆昨日の目標→その結果☆
◎朝6時に起きる→☓
◎毎日情報を発信する→☓
◎毎日仕事以外の人に話掛ける→◯
◎腕立て・腹筋30回→☓
◎自宅のある12階まで歩いて登る→☓


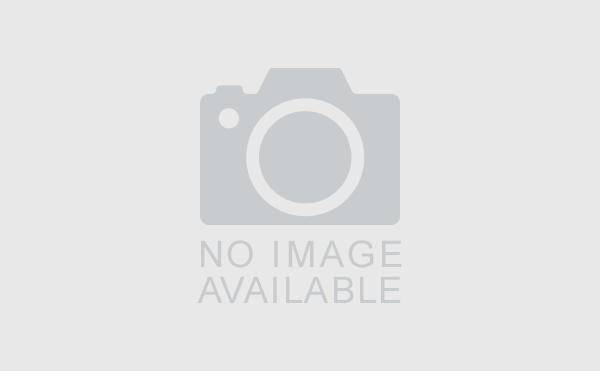
“阪神大ワインフェスタがクリアした試飲販売会の課題とは?” に対して1件のコメントがあります。